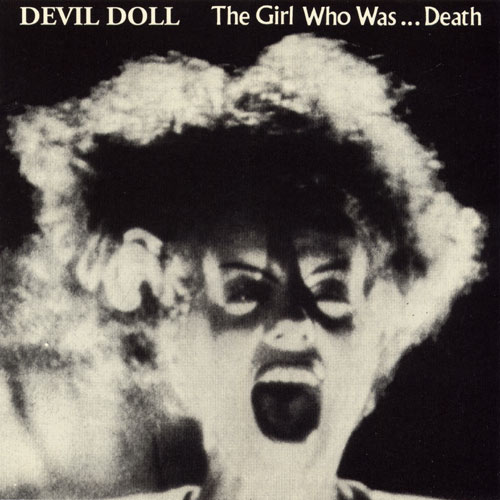Vampyr
監督:Carl Dreyer
主演:Julian West
時間:73分
1932年ドイツ=フランス合作映画。監督はオランダ出身のカール・ドライヤー。そしてほとんどのシーンは映画の舞台でもあるクールタンピエール(Courtempierre)で撮影されたという。また映画のキャストのほとんどは素人の役者で、プロなのは、領主を演じたMaurice Schutz、その娘で吸血鬼に蝕まれる役を演じたSybille Schmitzだけ。主演のアラン・グレイを演じたのはJulian Westとなっているが、それはこの映画の出資者であるロシア系貴族、Nicolas de Gunzburgの変名であり、つまりはパトロンがちゃっかり映画の主役をやっちゃっているのだ。自分で「お金は出すから主演させて」って言ったのだろうか。べつに演技はうまいわけでもないが、それほど演技力が必要とされる役でもないし、また全体の退廃的雰囲気によく合致しているので、結果的にナイスキャスティングだと思う。
多くの吸血鬼映画がその原作に、ブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』(1897)を据えている一方、この映画はシェリダン・レ・ファニュの作品集『鏡の中をおぼろげに(In the Glass Darkly)』(1872)を原作にしている。これは「第一コリント」13:12
βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αίνίγματι,
というのも、我々はいままさに、鏡を通しておぼろげに見ているのだから。を基にしている(原文では「中で」ではなく「通して」)。 ドライヤーはこの作品集のなかでも、とりわけ「カーミラ(Carmilla)」と「The Room in the Dragon Volant」を基にしているという。自分はこれら未読なので、どの程度の類似性があるのかは分からないが。
この映画、そもそもストーリー自体が曖昧模糊としており、しかも撮影そのものが、カメラの1メートルほど前に薄いガーゼをかざし、それを通して撮られたため、画面全体がまるで夢の中にいるようにぼやっとしている。公開当初は悪評紛々で、ドライヤーのキャリアに甚大なダメージを与えてしまった。ヴェネチアでは、観客が返金を求めて暴動にまで発展するありさまだったという。現在はむしろ再評価の機運が高まっている。
登場人物
- アラン・グレイ
- 領主
アラン・グレイが泊まっている宿屋に彼が訪れたことによって、話は動き始める。しかし、いきなり音もなく他人の部屋に忍び込むとか、この人も大概である。なんでそんなビビらせるような登場の仕方をするんだ!?しかも、意味深な会話を交わした後、「私の死後に開封するように」という包みを置いて去っていくし。初見では絶対信用されないような行動ばかりする。後にアラン・グレイが彼の館を訪れた際に、何者かに撃たれて死亡。映画後半には、自らの敵に復讐するために霊となって(?)一瞬だけ登場。元祖フォースの使い手?
- ジゼル
領主の娘1。素人の役者で、演技自体は大したことなく、まるでマネキンのようにぎこちないのだが、映画全体の雰囲気と相まって、それ自体異様な雰囲気を醸し出している。叫びこそしないが、基本的に周囲の状況に翻弄されるだけの役柄。終盤誘拐され、監禁されるのだが、何とも言えない無機質なエロスがある。
- レオーネ
領主の娘2。こちらが姉?登場シーンから寝込んでおり、領主のセリフから、これまでもたびたび傷を負っていた(吸血鬼に狙われていた)ようで、登場はベッドの中がほとんどである。「私汚されてしまったの…」と泣いたあとに周囲を見る目付きの異様さは、さすがプロの役者。最終的には吸血鬼の呪縛から解放されるのだが、そのときにベッドから起き上がる様子もすごかったため、セリフで「解放された」と言われなかったら、またなにか怖いことが起きるのかと邪推してしまった。
- 医者
領主の館に訪れ、レオーネの看病をしている。一見いい人なのだが、吸血鬼の手下。ジゼルが「なぜお医者様は夜にしか来ないの…?」と召使に聞いたり、謎の老婆と一緒に登場して(これが吸血鬼)、毒薬の瓶を手渡されてニヤニヤしていたりと、いろいろ伏線はある。映画全体のストーリーが分かりにくいため、初見では気付きにくいのだが、初登場時から、実は吸血鬼と行動を共にしている。最後は製粉所のケージに閉じ込められて、上から落ちてくる粉(小麦粉?)に埋まって圧死。
- 召使
領主の館に仕える、年老いた従僕。ものすごくいい人。しかも、実質この映画を解決した人。領主とその二人の娘に甲斐甲斐しく仕える、朴訥で善良な老人として描かれており、まぁ雰囲気だけの役柄なんだろうなと思っていたら、アラン・グレイが置き忘れた吸血鬼にかんする本(領主の遺品)を読み、吸血鬼の正体を発見し、吸血鬼の墓を掘り返し、退治する(実際に杭を打ち込んだのはアラン・グレイだが)。また、吸血鬼の手下の医者を製粉所に閉じ込め、圧殺するという、無慈悲な処刑も行う。彼がいなかったら、クールタンピエールの村は滅んでいたんじゃないだろうか。
- 吸血鬼
吸血鬼、マルグリット・ショパン。吸血鬼と言えばドラキュラのイメージが強いなか、女性、しかも老婆の吸血鬼。昔クールパンティエールの村で大量の犠牲者を出したという。領主が遺した本にその事件について書かれていたおかげで、召使はマルグリット・ショパンの墓を突き止めて、その胸に杭を打ち込むことが出来たのだが…。あれ?そうなると、本に書かれていた退治法で実際に退治されたのは誰?あまり細かいことを気にしちゃダメか。医者と退役軍人の二人を従僕として使役しているが、かつては村全体を支配したにしては、なんとも限定的な影響力。
印象的な場面
この映画は雰囲気作りがきわめて巧みである。映画自体の統一感が物凄いのである。冒頭、宿泊した宿屋の壁に掛けられていたタペストリーをアラン・グレイが見るシーンであるが、おそらく「死を忘れるな(Memento Mori)」などをテーマにした絵画がまさに映画とマッチしている。
同様に、アラン・グレイが泊まった宿屋で、二階から不明瞭な声が聞こえてくると思い、様子を見に行ったところ、扉から現れるのがこの老人である。この異様な雰囲気!アラン・グレイもビビりまくって部屋に鍵かけたりしていたが、のっけからこれとは、掴みが強烈である。しかしこの老人、このシーンだけの出演で、基本的に雰囲気要員。
館に行く前に、アラン・グレイが迷い込む城も幻想的な雰囲気を醸し出している。とくに影の使い方がとてつもなく上手い!ここでは退役軍人がベンチに座っているのだが、実は彼の横に座っている影、彼とは別に独立して動いているのだ。その後もダンスシーンが流れるのだが、それも踊っている影が延々と映されるだけ。白黒という映画の特色を最大限まで活かした手法だと思われる。
有名なシーン。幽体離脱したアラン・グレイが自らの埋葬シーンに直面するという幻想的なシーン。しかしこのシークエンス、普通に物語のメインストーリーの中に組み込まれているので、これ自体夢なのか、それとも現実なのかがハッキリしない(まぁ現実だったらわけわからないことになるのだけど)。1932年の時点で、このような半透明処理が出来たのか、というのも驚き。
誘拐され、監禁されているジゼル。この姿のまま微動だにしない。この人間性の無さ(役者が素人で苦悶の演技が出来なかっただけ、という可能性もあるが)が、ジゼルという役柄に無機質なエロティシズムを付与している。
最終的に脱出して、二人ボートに乗るアラン・グレイとジゼル。この後彼らは岸辺に着いて、それから森の中を抜けていくのだが、その向こうには光が差しており(映画内の時間としても、夜明けが来たということの表現?)、二人の未来にたいする希望が示唆されている。霧のなか、彼方から聞こえてくる声に「アロー」と応える二人の姿は幻想的で美しい。
しかし映画の最後を飾るのは、吸血鬼の手下の医者。彼が窒息死するところで映画は終了するのだ(このシーン自体はそのちょっと前)。惨劇から脱出する、二人の未来に満ち溢れたシーンではなく、製粉所で圧死する敵の死のシーンで映画を締めくくるドライヤー監督の手法は面白い。単なるハッピーエンドではなく、その裏に潜む残酷さが強調される形になっているように思われる。この辺りも、単純なハッピーエンドを好む観客からは余計に思われたのかもしれない。